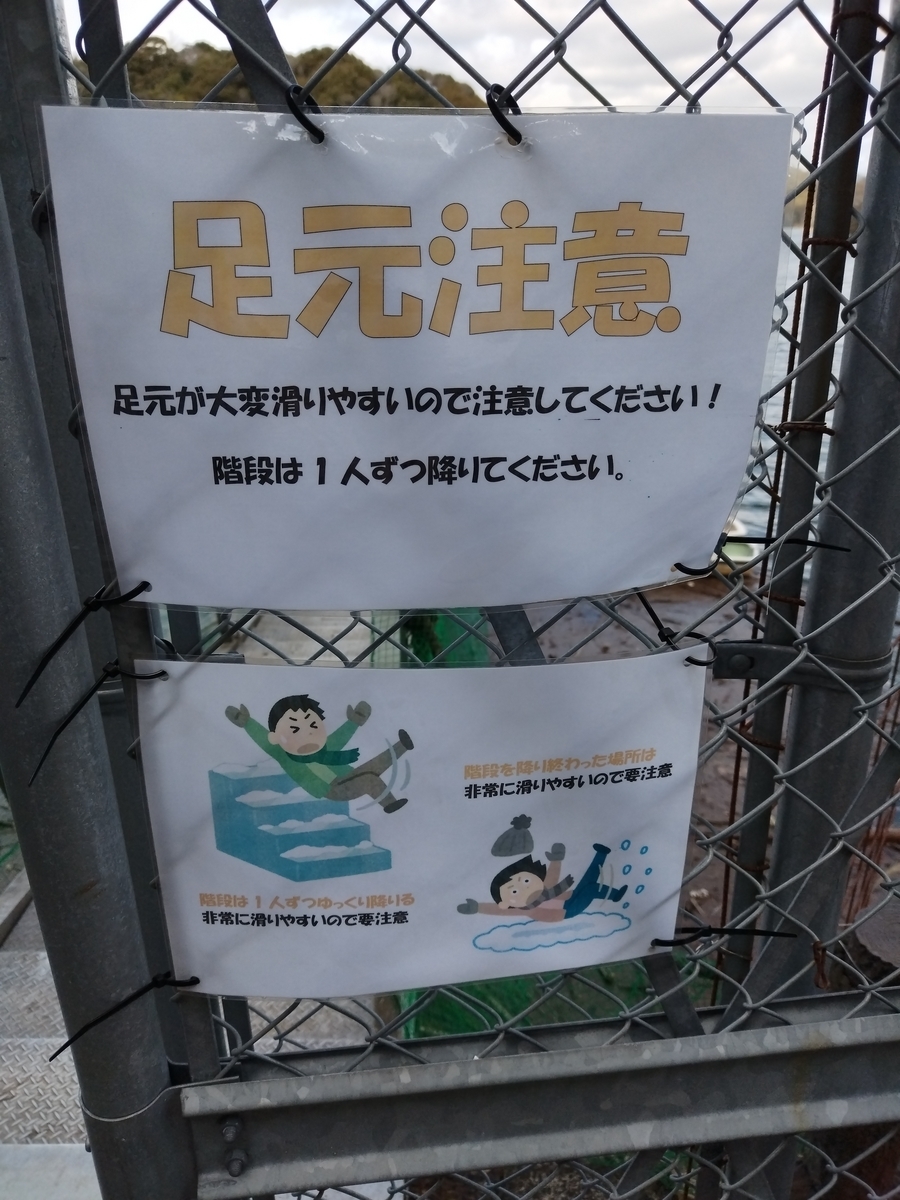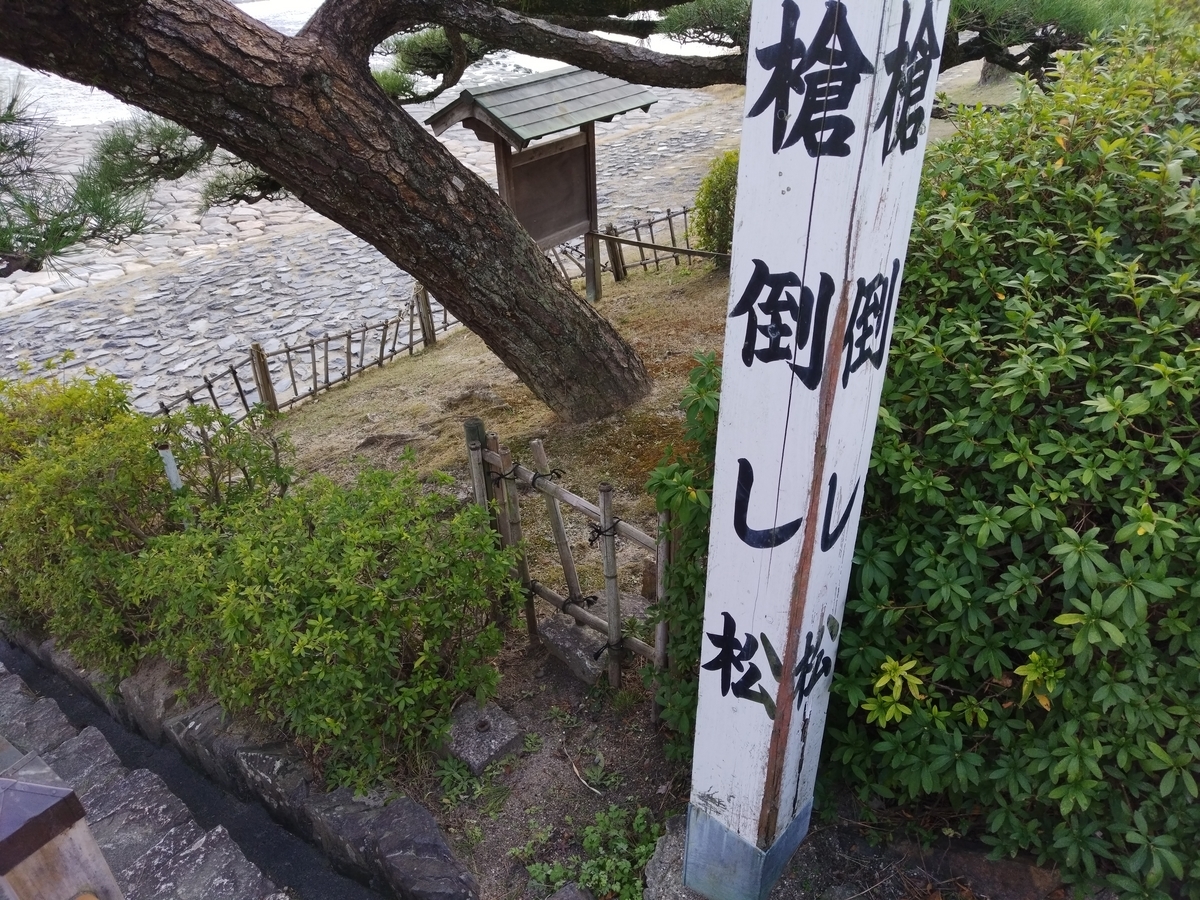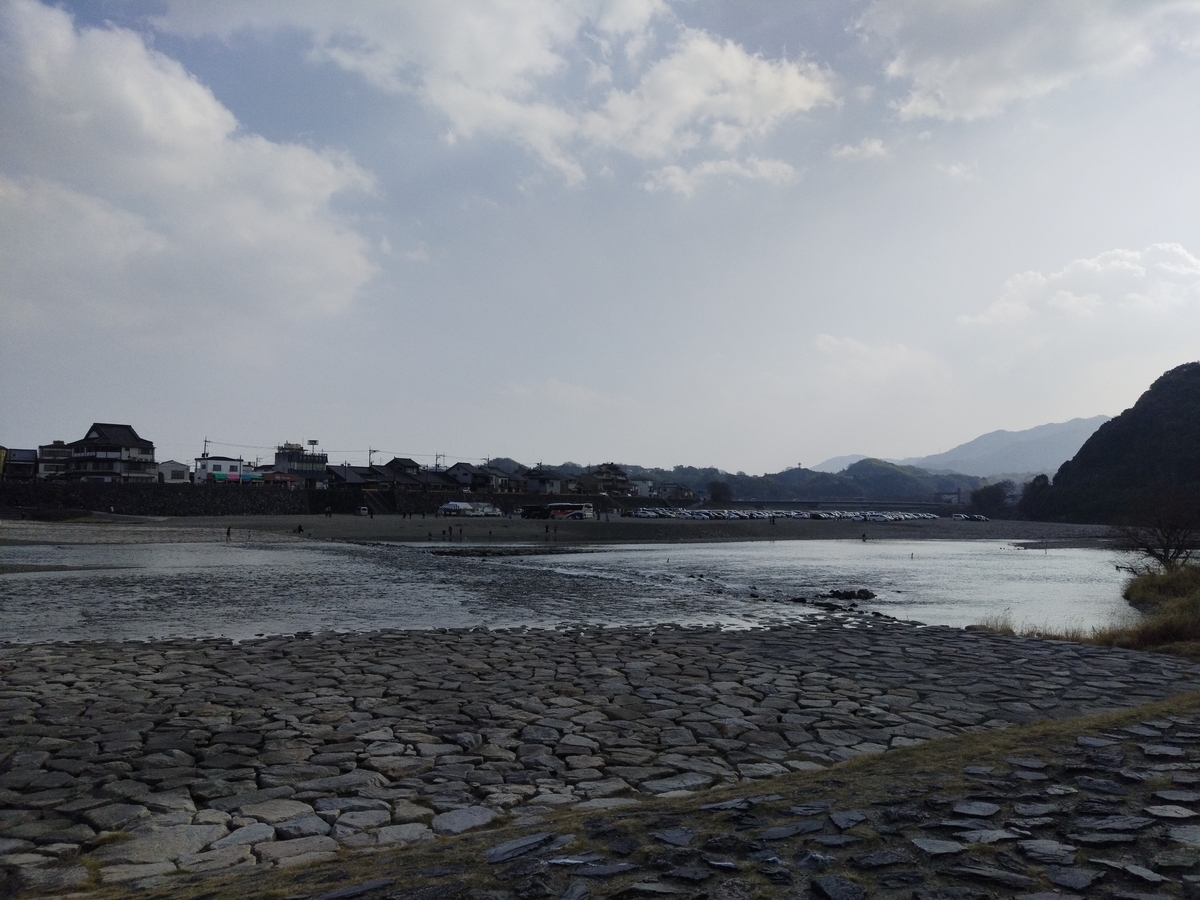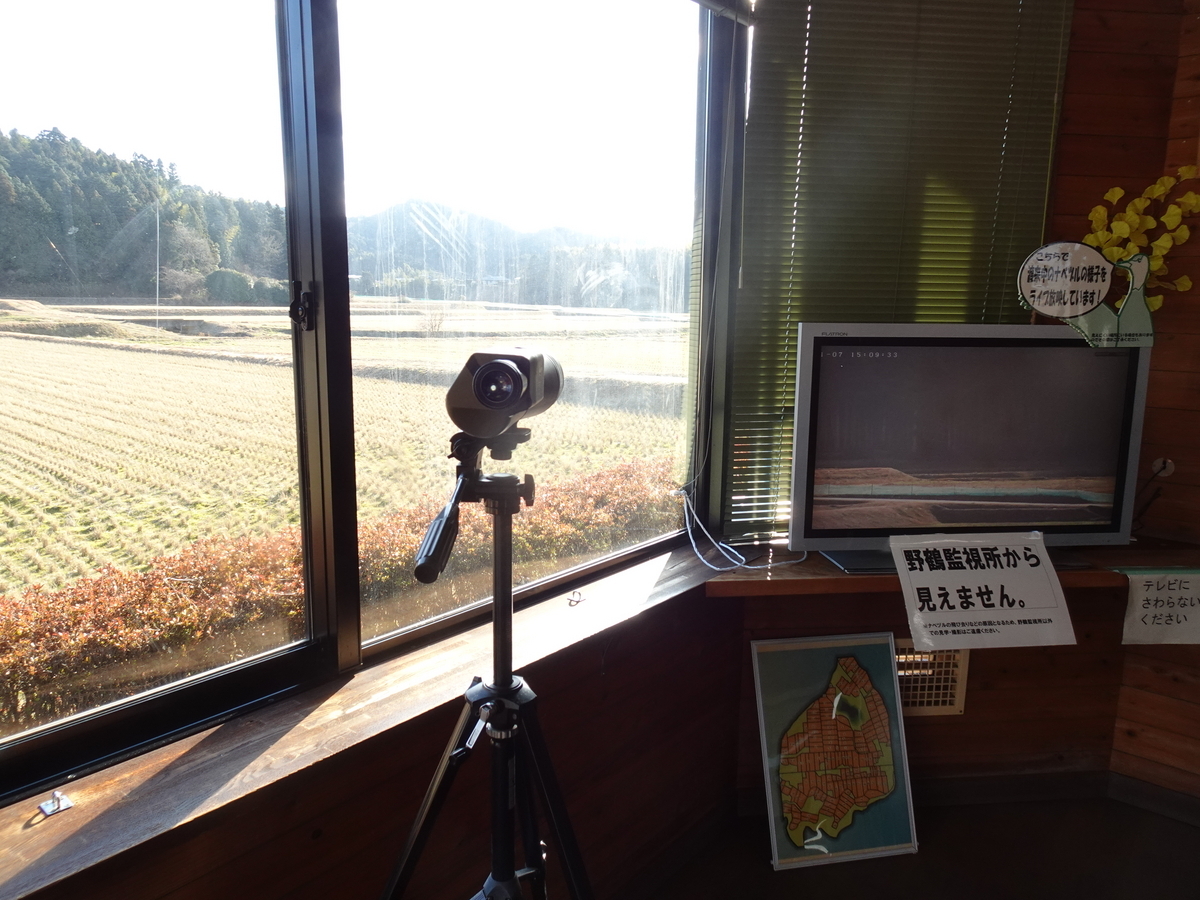山口県長門市の湯治温泉、俵山温泉の風景を紹介します。
俵山温泉とは
916年、地元の猟師が白猿に導かれて発見されたとされる温泉です。
そのため町中に「白猿山薬師寺」、猿まんじゅう、猿の絵が道路に描いてあったり、猿にまつわるものが沢山あります。
↓これが町の中心の解説板なのですが、後ろにこっそりお猿が3匹います ※石像

温泉としての特徴は高濃度のアルカリ性の温泉水は強い酸化還元力があるとされ、療養・美肌によいといわれています。
※この温泉の素晴らしさは別格だと思います。
ただこのあたりは私なんかの説明よりも、多数でている専門家の解説に譲ったほうがよさそうです。
俵山温泉の風景
俵山温泉の風景をいくつか撮影してみました。
私も歳をとるにつれて、温泉地を訪ねる回数が増えてきました。
ただ、ここほど古い温泉の街並みを残せているところは見たことがありません。
実は「町の湯」に入りに立ち寄っただけですので撮影個所は一部ですが、まだまだ面白いところは沢山あります。
温泉街の入口に当たるところ
温泉街の始まりがこのあたりになります。
「三猿まんじゅう」と書かれた建物があります。
この饅頭は俵山の名物で、今も販売されています。
※撮影し忘れましたが、出来立てが食べられるお店があります。

中心の通り(入り口前)
少し先に進むと両側に旅館が、ひしめき合っています。

中心の通り(町の湯前)
「町の湯」という温泉の前から、通りを撮影してみました。

「町の湯」の外観
俵山温泉に来たら、この「町の湯」は外せません。
実はこの俵山の旅館のほとんどは旅館内に温泉がありません。
共同浴場の「町の湯」に入る湯治スタイルなのです。

私がこの「町の湯」に最初に来たのは、大学生の時で友人に教えてもらってきました。
今では私が周りの人にお勧めしています。

俵山には「町の湯」の他にも、以前「川の湯」がありました。
現在は「川の湯」がなくなり、源泉は「白猿の湯」に引き継がれています。
それぞれ源泉の効能が違うので、自分に合った湯を選択するのも良いです。
「町の湯」の飲泉所
「町の湯」の湯は透明なわりに硫黄の香りが強いですが、温度がちょうどよく入りやすい湯でした。
それでいていつも悩まされる肩こりが、かなり和らぎました。
せっかくなので帰りに飲泉所で温泉水を飲みました。
とても飲みやすかったので、ペットボトルで購入しました。

熊野神社付近の駐車場
今まで私は「俵山湯町第1駐車場」に停めていました。
ただこの駐車場は町の中心の細い道を通っていかねばなりません。
そのため、大きな車は厳しいものがありました。
しかしいつもの所と別に温泉客用に自治体が解放している駐車場が、熊野神社付近にありました。

ただ、長期間の駐車はダメです。
ルールは守らないといけないですね。
アクセス
最寄り駅はJR美祢線の湯本温泉駅です。(俵山温泉に行くのに)
ですが、歩いていくのは大変な距離なので、レンタカーがお勧めです。
以上です。







 桟橋への移動
桟橋への移動